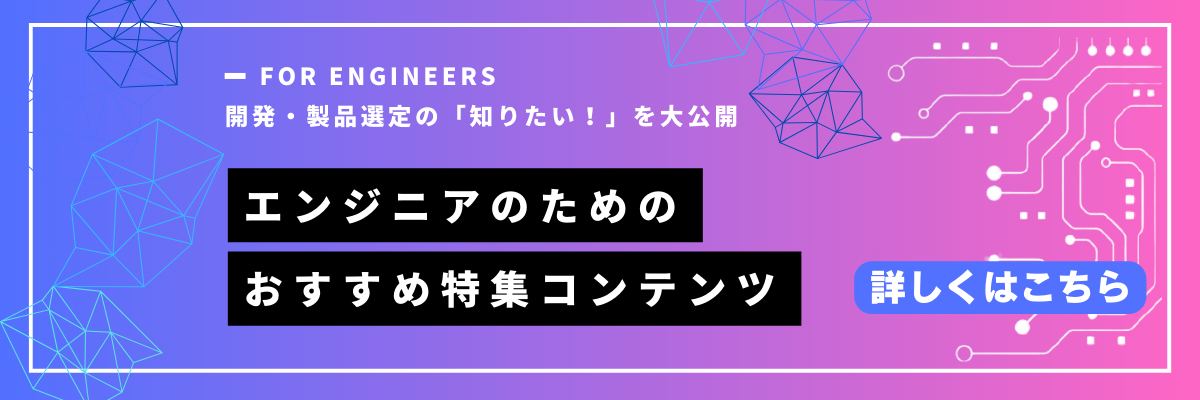ノーベル賞学者に学ぶ仮説の重要性 どう立てる?何に役立つ?
~よい仮説とはどのような仮説か、それを作るにはどのような手順を踏めばいいか~
ナレッジ

目次
よい研究をするうえで、よい仮説を立てることは大変重要です。しかしその方法を体系的に習うことは実はあまりなく、実際に研究を行う過程で各自が見よう見真似で体得することが多いようです。
そこでこの記事では、研究を行う上で大変重要な、よい仮説とはどのような仮説か、それを作るにはどのような手順を踏めばいいかを解説します。
あわせて、このスキル(科学者的思考法)が実生活でどのように役に立つかについても紹介しますので、参考にしてください。
研究を行う上で大変重要な仮説
研究者はやりがいのある素晴らしい仕事のひとつです。研究者の仕事の中心となる研究ですが、その一般的な流れは、仮説を立て、それを実験やシミュレーション、調査などで検証し、結果を考察したのち、論文や学会で発表することです。
このように仮説を立てることは研究の最初に行うことになります。仮説が立てられなければ研究を開始できませんし、研究のスタートと同時におかしな方向に向かってしまっては、ゴールに到達できません。
おかしな方向というのは、仮説が検証できてもそれが意味のないものであったり、すでに知られているものであったり、そもそも仮説が検証できないなどの場合です。ですからよい仮説を立てることは研究を行う上で大変重要です。
しかし、よい仮説を立てるのは難しく、それを最初にしなければいけないことは研究の大きなハードルとなります。そこで仮説の立て方について順を追ってみていきましょう。
仮説を立てる方法
それではより具体的に、仮説を立てる方法を紹介します。仮説を立てる際の一般的なステップは、
1. 先行研究の調査
2. 仮説を立てる
3. 思考実験
4. ブラッシュアップ
という流れになります。
思考実験やブラッシュアップの段階でその仮説が不適切と判断された場合は、最初に戻りますが、その過程で何がわかっていて、何がわかっていないか、それを検証するにはどうしたらよいか理解が深まるため無駄にはなりません。
先行研究の調査
まずは先行研究の調査です。インターネットを用いて論文を検索します。論文の多くは査読というプロセスを経て、その質が一定以上を満たしていなければ採択されません。
これに対して様々なブログなどの文章は科学的な検証が行われていないため、信頼に値しない場合が多く、注意が必要です。
また研究論文においては、これまでの研究論文から、何がどこまで分かっていて、どこからが分からないか、他の論文を参照しながら文章で示す必要があります。
そのため、信頼できる論文を用いて事前調査をすることは、自身が論文を書く段階でも不可欠です。
論文を検索するには、Google Schlar、CiNii、J-STAGEなどが用いられます。
論文を読むというと難しく感じるかも知れませんが、論文を通じて学術的な文章に触れる経験は、論理的な思考を身につけるのにも役に立ちます。
多くの仮説を立ててみる
先行調査で研究の可能性を見つけたら、仮説を立てます。仮説は多く立てた方がよいものに出会える可能性が高まります。少なくとも10くらいは仮説を立ててみましょう。
ブラッシュアップ
仮説が立てられたら、それを評価します。学術的に新しいか、役に立つか、検証可能かなどについて考えます。
ある程度考えてそれ以上出なくなったら、ぜひ知り合いや先生に話してみましょう。問題が見つかることはもちろん、改善方法や新しいアイデアをもらえることもあります。沢山の仮説の中で、自分が解くべき問題を絞り込んでいきましょう。
そもそもよい仮説とは?
仮説を立てる際には、よい仮説とは何か知っておくとよいでしょう。そうでなければ仮説の良し悪しを判断できません。そもそもよい仮説とは、どのような仮説を指すのでしょうか。
よい仮説とは、それが検証されることで、今まで分からなかった新しいことが明らかになったり、役に立つものを指します。
もちろん新しいことがわかり、世の役に立つのが望ましいのですが、そのような研究は実際にはほとんどなく、研究により「新規性」と「有用性」の2つの度合いは異なります。
一般的には理学系では科学としての新規性が強く求められ、工学系や農学系では新規性と同時に有用性がより重視されます。
これに加えて大事なのが、その仮説を検証することに対する自身の好奇心です。卒論でも最低半年程度、修士論文でも1年以上掛けて検証するわけですから、モチベーションを維持する上で好奇心をもてることは大切です。仮説を立てたらそれがワクワクするかについても考えてみることをおすすめします。
もうひとつ大事なことは、仮説の検証が失敗に終わっても意味がある仮説にすることです。これによって結果がどちらに転んでも成果を得られます。
仮説を立てるプロセスの例
もう少し具体的に、実際に仮説を比較しながら、仮説を立ててみましょう。
たとえば、
「血液型がA型の人は、まじめである」
という仮説を思いついたとします。
このように仮説は、少なくとも2つの物事の関係性を示すものです。ただし相関があることと因果関係があることは違いますので注意が必要です。
また上記の仮説では、A型の人についてしか分かりません。
そこで、
「血液型とまじめさには関連がある」
にすると全ての人に当てはまり、多くの人に役立つでしょう。
さらに、
「血液型と性格には関連がある」
ですと、まじめな性格以外にも適用範囲が広がります。
ある程度仮説が出来てきたら、Google Scholarなどを用いて、先行研究を探してみましょう。
サイトの検索窓に「血液型 性格 関係」と入力して検索すると、沢山の先行研究が出てきます。したがってこの仮説が多くの人にとって興味深い仮説であることがわかります。
一方で、いくつか読んでみると、残念ながらこの仮説は否定され、その際のサンプル数も1万人程度であることから、既に検討の余地がないこともわかります。
このような作業を繰り返していくと、どのような研究が既にあるか分かることはもちろん、対象の知識も深まり、よりよい仮説に近づいていきます。失敗とは考えず、前向きに次のステップに移りましょう。
最近ノーベル医学生理学賞を受賞したスバンテ・ペーボ博士は、人類(ホモサピエンス)の起源を探るために、ヨーロッパから西アジアに生息し、4万年前までに絶滅したネアンデルタール人のDNA解析を試みました。つまり「ネアンデルタール人がホモサピエンスの起源」との仮説を立てたわけです。
ネアンデルタール人は4万年前までに絶滅したのですから、その遺伝子を分析する試みは困難を極めます。そこで当時の学者の多くはDNAでは検証が不可能と考えて、人類の骨や歯の化石を用いて研究を行ってきました。
ところが困難の末に得たDNAの解析結果から、ネアンデルタール人がホモサピエンスの起源ではないことがわかりました。
これは、ホモサピエンスの起源をネアンデルタール人から知ることは出来ないことを意味しますから、その時に博士は落胆したかもしれません。
しかし考え直し、今度は「ホモサピエンスとネアンデルタール人は共存した」という仮説を立てます。その検証のために現在の人類のDNAを解析して、DNAの1%から4%がネアンデルタール人のものであることを明らかにしました。
つまり、仮説は立証され、ネアンデルタール人とホモサピエンスは一時期共存していたこと、ホモサピエンスの拡がりが、アフリカから中東、ヨーロッパ、アジアなどの順序であったことが明らかになり、人類学や考古学、歴史学など多方面に大きな貢献をしたのです。*1
このようにノーベル賞を受賞したペーボ博士ですら、その道のりが平坦ではなかったことや仮説検証に失敗しても次に活かす姿勢はたいへん参考になります。
仮説の立て方を習得すると実生活にも役に立つ
仮説が立てられるようになると、研究はもちろん実生活のさまざまな場面で役に立ちます。いくつかの例をみていきましょう。
情報収集力アップ
仮説を立てる際には、その仮説がすでに検証されていないか事前に調べておかないと時間と労力を無駄にしてしまいますが、先行研究の調査の過程で文章から本質を読み取る能力が身につきます。
その技能は生活の様々な疑問を解決する上で役に立ちますし、デマなどに対して自身で信頼度の高い情報を調べることができるようになります。
仮説を捨てるプロセスが役立つ
研究の初期段階では、様々な仮説を立ててそれを評価することになります。解くべき問題が星の数ほどある中で、何に注力するかを考えることは様々な決断の際に役立ち、自身を知ることにつながります。
仮説を立てた上で、この問題を解くのはよそうと仮説を捨てる作業も、日常生活で役に立ちます。自身の判断や考え方の傾向を知るなかで、様々なバイアスに左右されない意思決定力が身につくでしょう。
また大量の仮説を捨てる過程で、間違うことや失敗に対して前向きになれるようになります。そもそも世の中の全てが解るはずはないという謙虚な姿勢でいられ、失敗からも学べるようになります。
コミュニケーション力のアップ
自分が考えた仮説が未解明でオリジナリティーが高ければ高いほど、それは誰にとっても未知の領域になります。このような未知の問題について説明するには高いコミュニケーション能力が必要です。そのため仮説を立てて周囲の人に説明する過程でコミュニケーション能力が高まります。
仮説を立てて豊かな生活を
よい仮説を立てることは研究の根幹です。一連のプロセスは、研究の最初に行うものでありながら科学者的思考方法や文献調査など科学的な活動の多くを含んでおり、実生活でも大変役立ちます。
たとえば商品が売れないとき、売れない理由がわからなければ改善のしようがありませんが、その理由について考える過程は、仮説を立てる作業そのものです。
アプリの使い方などの知識は、インターネットで検索すればすぐにわかりますが、時代の変化とともにすぐに役立たなくなります。しかし科学的な思考方法はずっと使えるものです。
また仮説を立てるという作業は、自分の思考や理解を疑うことにもつながり、常に考えをアップデートすることにもなります。
まずは多くの仮説を立て、これと思った仮説を知り合いや先生に話してみてはいかがでしょうか。意外にも身近な家族が最も手厳しいかもしれませんが、その過程で様々な興味や関心を共有することもできるでしょう。
参考文献
*1
出所)科学技術振興機構「DNA解析で人類の起源と進化の解明に光当てる ノーベル医学生理学賞のペーボ氏は知日家」
https://scienceportal.jst.go.jp/explore/review/20221013_e01/
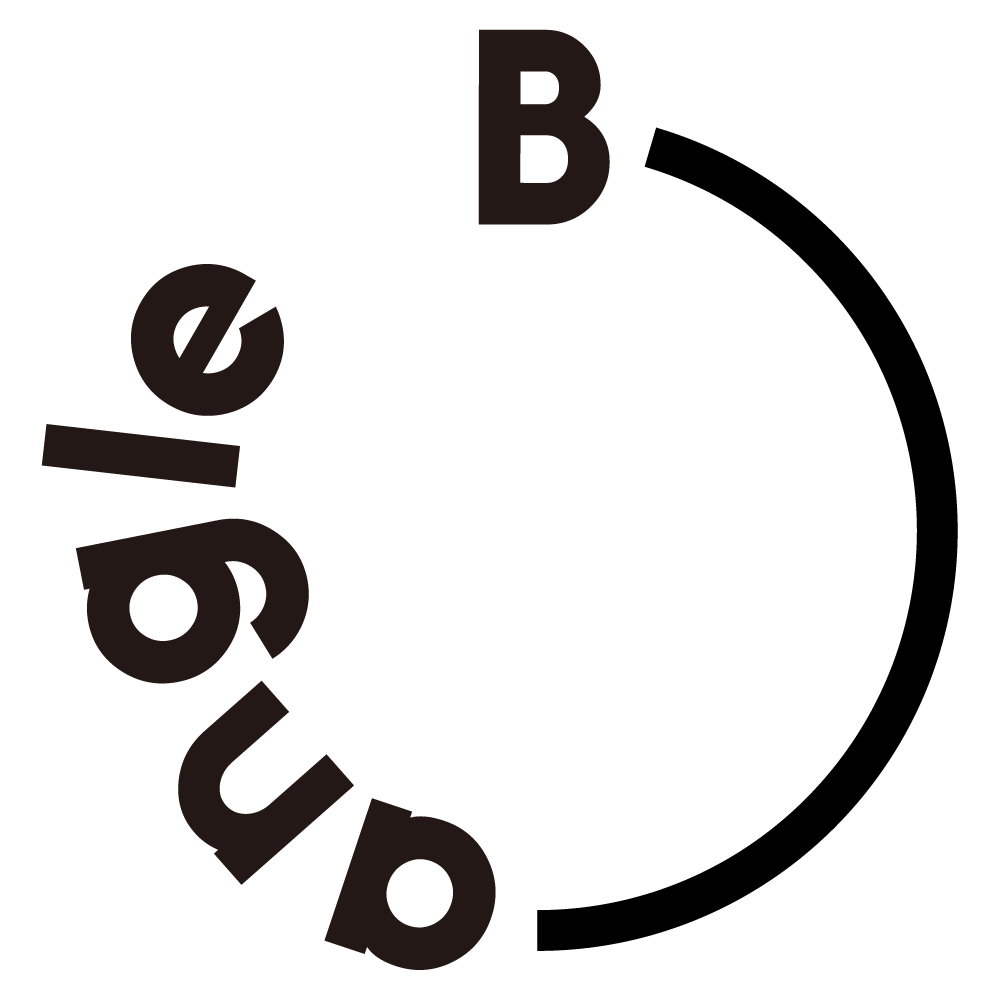
フリーライター
鯉渕 幸生 Yukio Koibuchi
Ph.D。米国標準技術研究所研究員、中央大学研究開発機構教授、Recora LLC 代表取締役CEOを兼務。沿岸環境の改善やそのためのドローンやロボットに関する研究開発に従事。ライターとしては、科学技術、環境問題、スタートアップ支援などのテーマで執筆している。